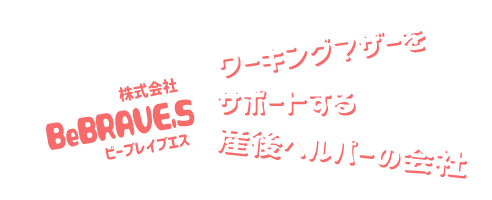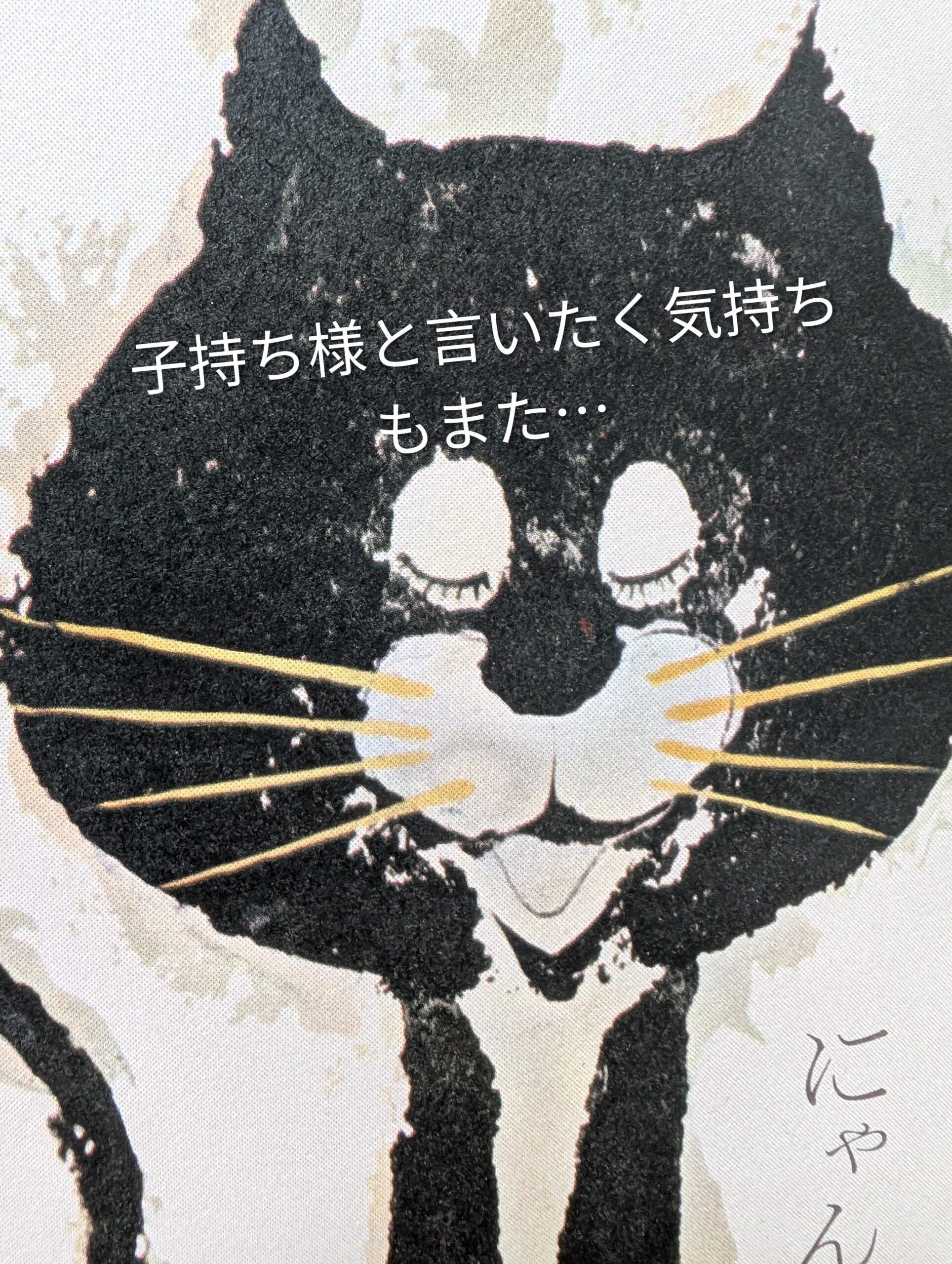こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。
今朝いつもと異なる時間帯にNHKラジオを聞いていましたら、「子持ち様」特集をやっていました。1年ほど前に、このブログでも取り上げたのですが、子持ち様とは、子育てをする人を揶揄する言葉です。育児をしていることを特権として、時短勤務や急な早退・遅刻をするため、そのしわ寄せが他の従業員にきてしまい、そのことが不満となって「子持ち様」という言葉に表れている⋯というものですが⋯
今回の特集では、番組に寄せられたメールから、いろんな声・意見が取り上げられていましたが、大別すると2つに分かれると思いました。
ひとつは、育児などに関する制度そのものを問題とする意見、つまり政策の問題点や企業の在り方を問うもの。もうひとつは、人(育児をする人や育児制度を使う人を子持ち様と揶揄・批判する人、育児をする人を子持ち様と揶揄する人を批判する人など)そのものへの批判です。
私が耳にしたときは、ちょうど、子持ち様などという言い方は心ない、今は昔と違って子育てについて知る機会や、かかわりそのもがないため、そういう心ないことを言う人が増えている、悲しいことだ、このような意見が紹介されていました。
かつて育児をした人からは、私たちの時代は育児休業などなかった。今は取るのが当たり前、当然の権利と思っている。そのしわ寄せは育児をしていない人にくる。自分たちは権利を享受しておらず、負担ばかりを押し付けられている、このような意見も紹介されていました。
制度や政策についての意見は(紹介されたものは)少なかったです。そのなかで公平な意見に聞こえたのは、制度はあっても、現場の対応は追いついていない。結局は現場の労働者が負担を強いられている、というものです。
制度そのものは実は先進国の中でも日本は決して劣っていないし、むしろ充実しています。育児休業の期間などは、アイスランド(男女平等でなにかと引き合いに出されるあのアイスランドです)よりも多いのです。これまでは制度はあっても飾りみたいで、運用されていない面がありました(育児制度に限らずね!)。
その反省から、やれ男性の育休取得何年までに何%だ、やれ復帰後の離職を防げ、やれ原職復帰だ(正規雇用)と、立て続けに法改正して制度をさらに充実させて、助成金で釣って法令以上の制度を企業に導入させて⋯
その挙げ句が子持ち様かよ💢ですね⋯
私は1年前と考えは変わっていません。子育て中の人は、子持ち様と言われるようなたいそうなご身分ではありません。今仕事をしながら子育てをしている人は自分の健康を慮ることさえできませんし、仕事をしていない人も、決して左うちわではありません。また、子持ち様と揶揄する人を心の狭い、狭量な人間と決めつけるのも問題の本質を見えなくしてしまいます。子持ち様と揶揄する人は実際に職場で負担を強いられている人だと思います。今の人は好きなだけ育休取って、そのしわ寄せは私たち年配者に!との不満も事実だと思います。
社会保険労務士法人に勤務していた頃、育児制度を法令以上に充実させた場合に出る助成金があり、それを顧問先の企業が導入しました。約1年後、そこの役員の方から、制度を廃止したいとの相談がありました。女性社員が何人も長く育休、時短勤務制度を使うので職場が機能しなくなり困っているとのことでした⋯
女性社員の境遇などその人を取り巻く環境はさまざまです。キャリア形成に対する考えも人それぞれです。でも制度があることで、使わないと損という空気も生まれます。社員の福利厚生を手厚くして会社が立ち行かなくなる⋯本末転倒です。
助成金の申請条件として、制度利用労働者と会社の担当者の話し合いというのは必須だったのですが、申請のために書くべきことは決まりきっており、形骸化していました。
話し合う、というのは、とりわけあうんの呼吸、空気を重視する日本社会では実はかなり難しいことです。
ラジオを聞いていてつくづく思いました。
人を批判するのは政策を批判するより簡単です。政策批判の場合、いつ、どこで、何を間違えたのか、精査が必要なので面倒くさいのです。