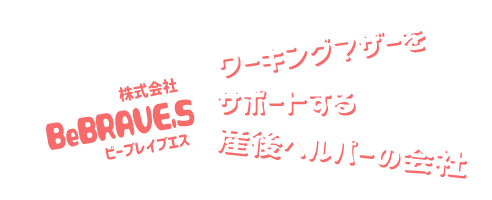こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。
さくらが満開ですね。ソメイヨシノだけでなく、ヤマザクラやオオシマザクラ、カンヒザクラなども7〜8割がた開花し、心を和ませてくれます。
小学校の入学式でしょうか、ランドセルを背負った新一年生とお母さんお父さんの姿をよく見かけました。
微笑ましい光景です😊
一方で、子どもたちを取り巻く日常、日本や世界の状況を考えると、複雑な気持ちにもなります。
1ヶ月後、数カ月後、1年後、今の笑顔で学校へ行けているか…突然の不意打ちのようなことが家庭に起きていないか…ケガや病気に襲われていないか…考え出すときりがありません…
親だけで子どもを守りきれるものではありません。
今回は、犯罪者から子どもを守るためにはどうしたらいいかということをお伝えします。
教育月刊誌「灯台2月号」に記載されていた神奈川県藤沢市の取り組みを参考にします。
大人はよく、怪しい人についていかないように、と言いますが、犯罪者の外見はごく普通で、子どもには(大人にだって)「怪しい人」かどうかの見分けはつきにくいのです。それなのに、防犯を呼びかけるポスターや看板にはサングラスをかけたオジサン・お兄さんがよく描かれています…
犯罪に巻き込まれないためには、犯罪が起こりやすい場所を学び、そうした場所に近づかない、その場所を通るときには細心の注意を払うといった取り組みが必要なのです。
では、どういう場所が危ないのか?
「入りやすく」 「見えにくい」場所です。
1.物理的に入りやすいのは住宅街です。そして見えにくいのは、塀や垣根が高く家の中から道路の様子が見えにくい場所です。高齢者の多い昔からの住宅街はそういうお家が多く、また、いつの間にか空き家になっていることも多いのです。
2.一見、見通しがよい田畑が広がっている場所も、広すぎて、そこにいる人物への注意力が低下するので危ない場所と言えます。
3.心理的に入りやすく見えにくいのは、駅やショッピングモールなど不特定多数の人が集まる場所です。多くの人が集まることでお互いの注意力が散漫になります。
4.落書きやゴミが放置されている場所は、地域の関心が低く、手入れが行き届いておらず、犯罪者からは好まれます。
地域の方やPTAなどでのパトロールはルートを固定しないランダムパトロールが一般的です。その背景にあるのは、犯罪者から見るとどこにでもパトロール隊がいるような錯覚を起こさせ、犯行を諦めるだろう、という考えです。
しかしさまざまな研究で、犯罪が起こりやすい場所を重点的に回るホットスポットパトロールのほうが、防犯の効果が大きいという結果が出ています。
子どもを守るのは一義的には親の責務ですが、親だけでは到底守りきれないのです。地域の人と協力し、子ども自身も注意し、親子で学んでいくことが大切です。
年度始めで慌ただしく、心も体も浮足立っているかもしれませんが、まずは安全第一でいきましょう!