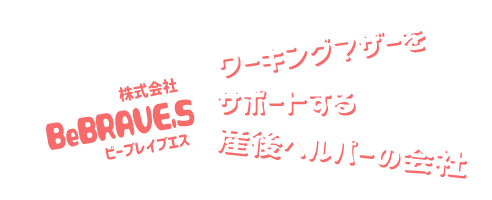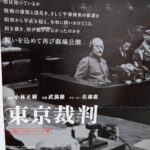こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。
暑い中にも秋祭りの太鼓練習の音が朝夕に聞こえてきて季節の終わりを感じます。
私が住む町内では獅子舞だけですが、今日訪れた宝達志水町では獅子舞と神輿があるようで、青年団の皆さんが公民館の前で休憩されていました。
本日同町の不登校支援施設おばちゃんちで、県政出前講座特別編「はせ、参じます」があり、主催者の方に誘っていただき、馳知事のお話を聞いてきました。
今日の出前講座は石川県の重点施策の一つである「成長戦略の実現」のなかの6つの戦略の一つ、「温もりのある社会づくり」で健康・子育て・福祉・男女共同参画などについて馳知事が県の取り組みについて話をされた後に質疑応答がありました。ヤングケアラーや不登校、ひきこもりといった内容にも触れていました。
最初の質問は、不登校経験者からの「ひきこもりは悪いことですか?」でした。
知事の回答は…
なかなかでした。私は日頃から「不登校」という言葉に対して疑問を持っていました。子どもが有する権利は「学校へ行くこと」ではなく、「教育を受けること」であるはずなのに、現状では学校へ行かないことはイコール教育を受ける権利がなくなってしまうことになっています。
学校の教科書は独学用にはできておらず、(問題の答えさえ書いてないことも)教師が学校で教えることで完成するように作られています。コロナ禍のときに痛感しました。
戦前の国民学校令なる、義務教育は市町村の学校によるという決まりがずっと踏襲されており、正規の学校(1条校とかいうのですか?)以外は認めないため、学校へ行かない=悪いこととなってしまっていて、これは大変に問題だということでした。
馳知事からこのような見解を聞けただけでも参加した甲斐がありました。県は横断的戦略として「デジタル活用の推進」も挙げていましたので、不登校支援との関連でこの点についても聞いてみたかったのですが、時間が少なく、質問したい方がたくさんいらして残念ながら質問はできませんでした。全児童生徒にタブレットを配布するなどというばかげたなんとか構想とかではなく(今はみなスマホを持っていますし、スマホで勉強もできますから。買えない家庭や子どもに提供すればいいだけです)、生成AIという汎用性AIが凄まじいスピードで発展浸透するなかで、子どもたちはどのように学んでいくべきなのか、県の掲げるデジタル活用とはいかなるものなのか、ぜひ知りたいところでした。
主催者が不登校支援施設運営者ですので、不登校児童の親御さんも当然お見えになっていました。自分たちの気持ちを知ってもらいたいという思いもありますし、県の取り組みについて聞きたいという切実な事情もあったと思います。
この点については少々納得いきかねる部分がありました。
親御さんたちは、県や市町や国になんとかしてくれなどとは言っていません。もう散々いろんな人、いろんなところで直接的間接的に責められています。学校へ行かなければ学ぶことさえできないなか(物理的にはネット環境があれば学べます。しかし、生成AIを持ち出すまでもなく、ネット検索でさえ汎用性が高ければ高いほど使いこなしには知性とスキルが必要です。これらを学ぶ機会は日本の教育にはありません)、教師からは忘れられ、適当にあしらわれるような態度に肩身の狭い不安な思いをしています。
知事は良くも悪くも元教員なのだなと感じました。教師に叱られ、政治家に叱られ、親御さんはいたたまれないと思います…
とはいえ、地方自治体のトップ自らが県民のもとに出向いて直接話をし、県民とやりとりするのはとてもいい機会です。忙しい身でありながら時間を割いていただき、ありがとうございました。
現職の県知事とお話する機会というのはなかなかありません。私は10年以上前、馳知事が国会議員だった頃、石川県里親会のバーベキュー大会でお話したことが一度あります。馳さんが里親さんとお話している間、秘書の方は子どもたちに水鉄砲で撃たれまくって討ち死にしてました(笑)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kouhou/demae/index.html